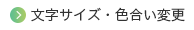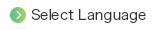洪水から身を守るために
情報防災部
危機管理室
危機管理・緊急対応係
近年、豪雨災害が局所化・激甚化・頻発化し、各地で甚大な被害が発生しています。 渋川市内でも洪水が発生するおそれがあります。 そのため渋川市は被害を最小限に抑えるため、洪水から身を守るための情報を改めて市民の皆さんへお知らせします。 洪水に...
防災関連情報リンク集
情報防災部
危機管理室
危機管理・緊急対応係
災害時に活用できる防災関連情報をご案内します。ご活用ください。 気象情報 キキクル(危険度分布)(気象庁)(新しいウィンドウが開きます) 高解像度ナウキャスト(気象庁) 防災情報 気象・地震・火山情報(前橋地方気象台) 群馬県防災ポータルサ...
ハザードマップ・浸水想定区域図(ため池)
産業観光部
農政課
整備係
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。 防災重点ため池マップ ハザードマップ 災害に強いまちづくり 浸水想定区域図 防災重点ため池マップ 渋川市内の防災重点ため池の名称・位置を掲載した防災重点ため池マップを公表しま...
災害時備蓄品について
情報防災部
危機管理室
危機管理・緊急対応係
渋川市の災害時備蓄品の現況 本市では、災害等発生時、家屋の倒壊等により生活が困難となった方に対し、最低限の食料や水、生活必需品の提供を行うため、災害時備蓄品の購入と管理を行っています。 本市における食料品等の備蓄状況は、「渋川市防災備蓄品一...