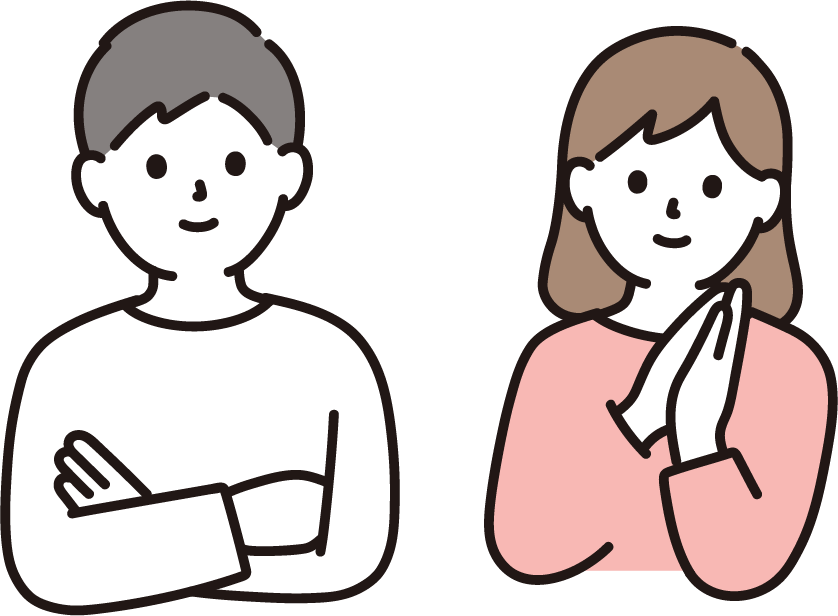 親「脱いだ靴は、履く時に履きやすいように、外側に向けてそろえておこうね」
親「脱いだ靴は、履く時に履きやすいように、外側に向けてそろえておこうね」 こども「分かってる」
こども「分かってる」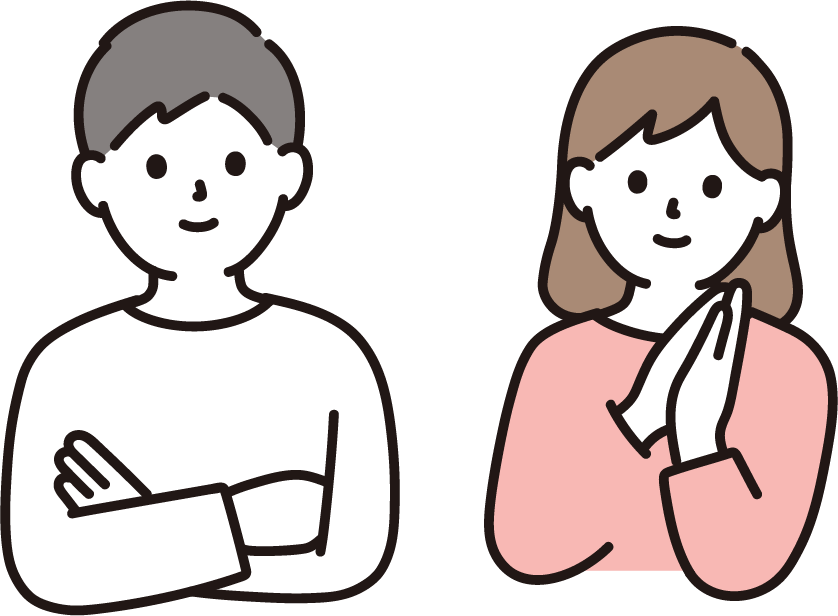 親「それでは、やってごらん」
親「それでは、やってごらん」「ほめトレ」とは、良好な親子関係を築くことを目的に、群馬県が取り組んでいる「ほめて育てるコミュニケーション・トレーニング」の通称です。
親が、こどもをほめる、認める、また、こどもの気持ちに共感することで、こどもの自己肯定感が高まり、親は子育て中の不安やイライラした気持ちが切り替わり、こどもと過ごす豊かな時間につながります。
ホームページと広報しぶかわで、毎月、日常生活の場面ごとに、言葉かけの良い事例を紹介します。
〈監修:県公認ほめトレ・トレーナー 坂井 勉さん〉
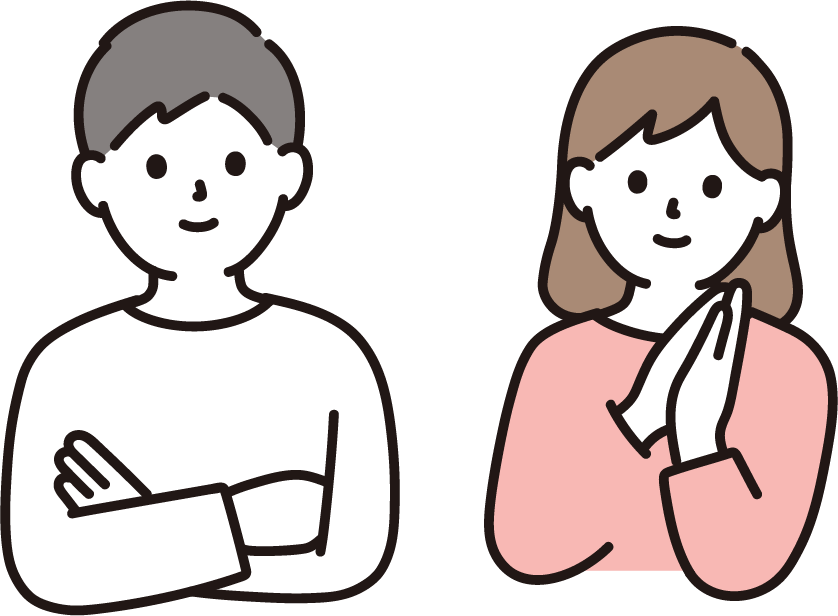 親「脱いだ靴は、履く時に履きやすいように、外側に向けてそろえておこうね」
親「脱いだ靴は、履く時に履きやすいように、外側に向けてそろえておこうね」
 こども「分かってる」
こども「分かってる」
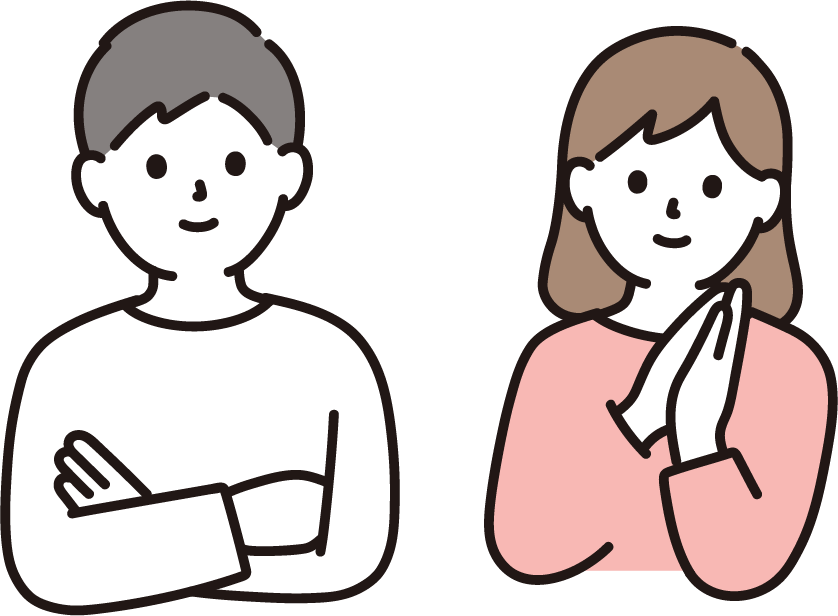 親「それでは、やってごらん」
親「それでは、やってごらん」
約束をした後、こどもが理解できたか確認したり、実際にやらせてみたりして、理解していなければ繰り返し教えることが大切です。こうすることで、「わからないからできない→できないから叱られる」のスパイラルから脱却することができます。
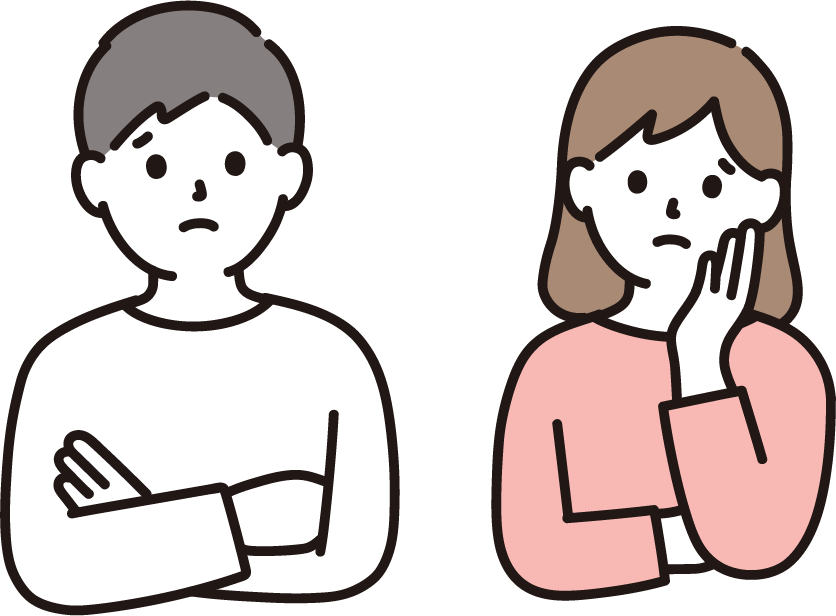 親A「おもちゃが出しっ放しじゃない!いつもやりっ放しなんだから。脱いだ服は片付けないし、飲んだコップはテーブルに置いたままだし。何回言ったらわかるの!」
親A「おもちゃが出しっ放しじゃない!いつもやりっ放しなんだから。脱いだ服は片付けないし、飲んだコップはテーブルに置いたままだし。何回言ったらわかるの!」
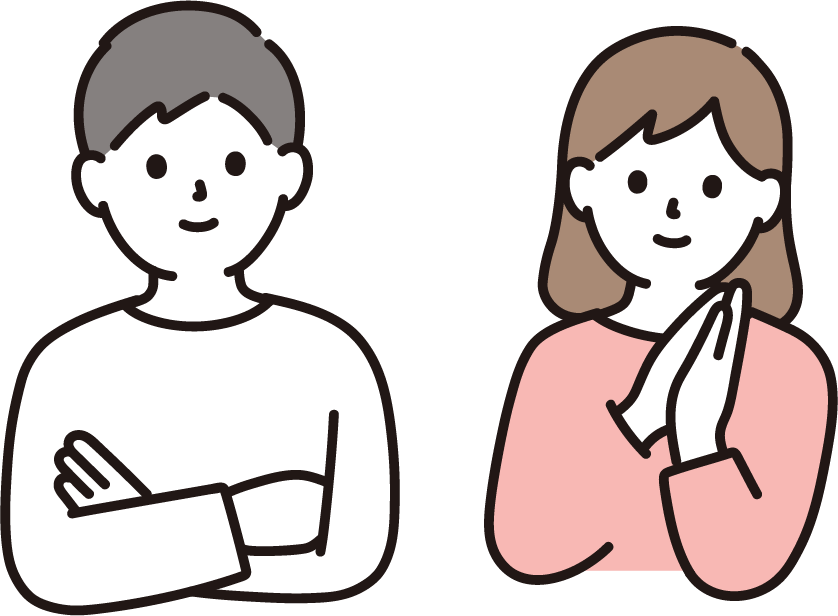 親B「おもちゃは、遊びが終わったら、この箱に片付けようね。」
親B「おもちゃは、遊びが終わったら、この箱に片付けようね。」
(こどもがおもちゃを片付けられたら)
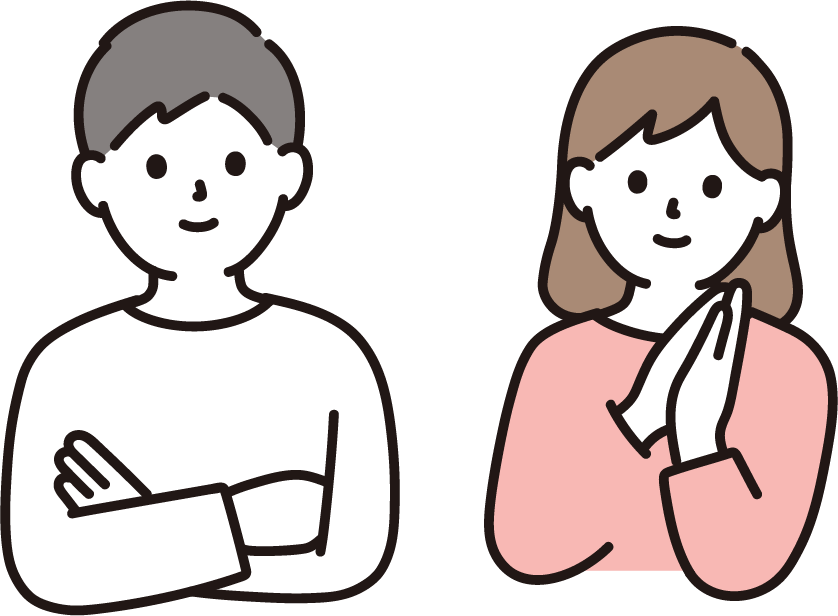 親B「きれいに片付けられたね。上手にできたね。」
親B「きれいに片付けられたね。上手にできたね。」
問題となっていることとは直接関係のない過去の出来事を次から次へと言ってしまうと、こどもは肝心なことが理解できなかったり、素直に従えなくなったりしてしまう恐れがあります。伝えるべきポイントを絞って、短い言葉で伝えましょう。
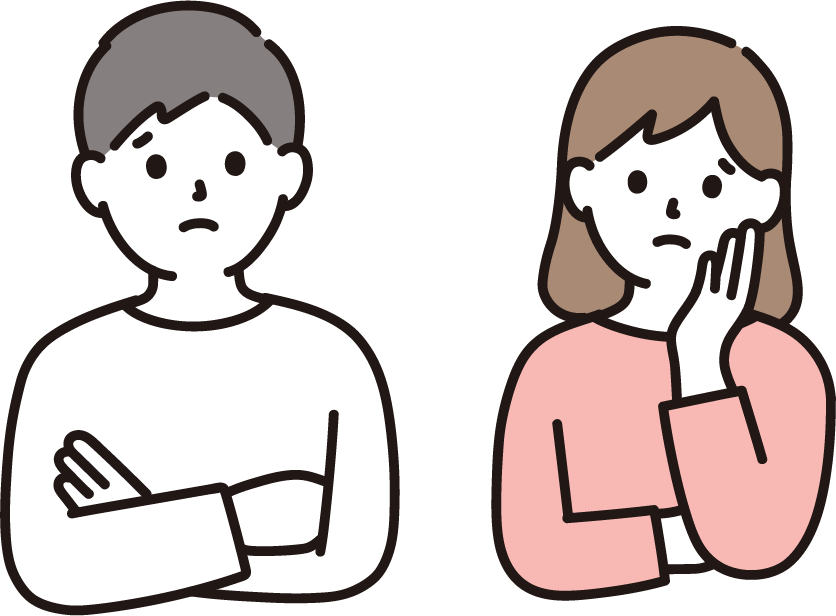 親A「積み木で遊んだら、ちゃんと片付けてね。」
親A「積み木で遊んだら、ちゃんと片付けてね。」
(結果→箱の中に積み木が山積みになって入っていた。)
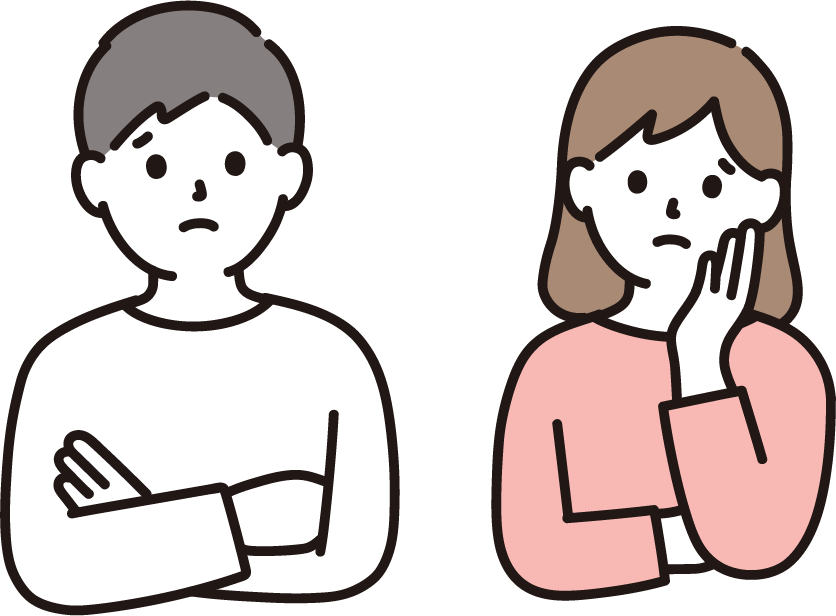 親A「ちゃんと片付けてないじゃない!」
親A「ちゃんと片付けてないじゃない!」
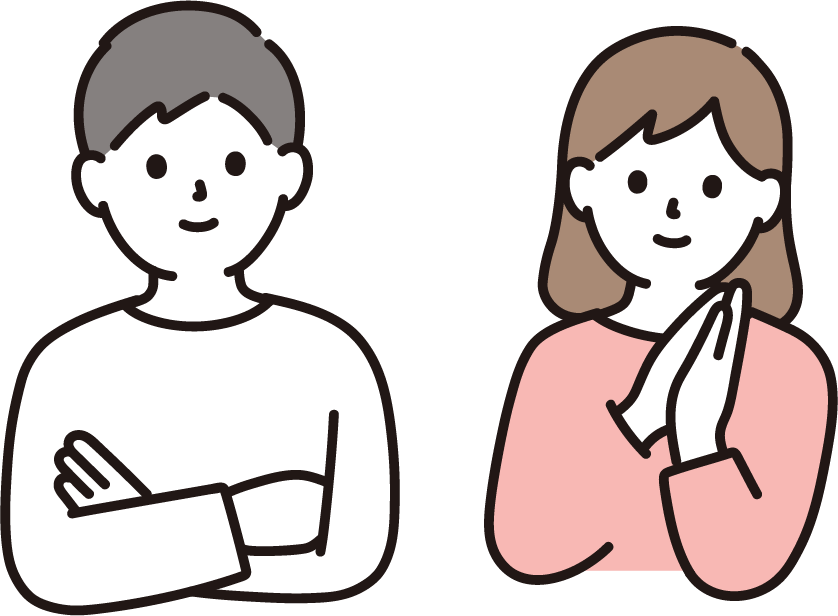 親B「積み木で遊んだら、元どおり箱の中に並べてしまってね。」
親B「積み木で遊んだら、元どおり箱の中に並べてしまってね。」
(結果→元どおり、箱の中にきれいに並べてしまわれていた。)
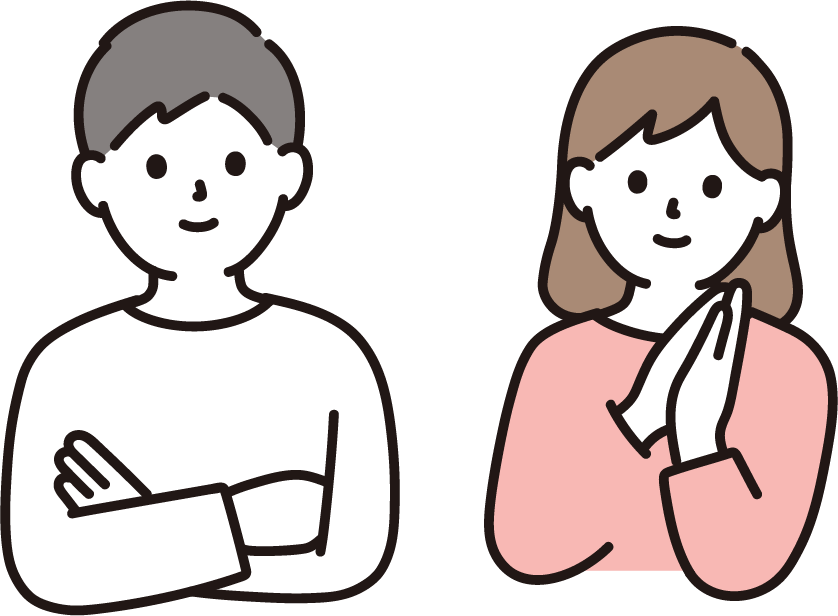 親B「きれいにしまえたね。」
親B「きれいにしまえたね。」
あらかじめ、こどもと約束する場合は、具体的に何をどうするかを伝えると、理解しやすくなり、言われたとおりに動きやすくなるでしょう。
どろんこ遊びをしていたこどもが、おやつの時間になったからと、手を洗ってきましたが、泥がよく落ちていません。
 こども「手を洗ってきたよ、早くおやつちょうだい。」
こども「手を洗ってきたよ、早くおやつちょうだい。」
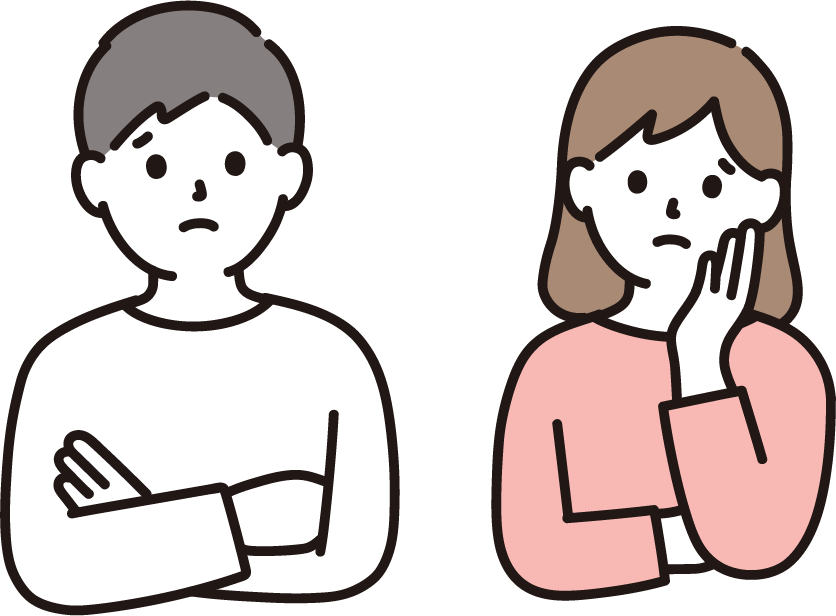 親A「なにこの手は!泥だらけじゃないの、本当に洗ったの?きれいに洗ってきなさい!」
親A「なにこの手は!泥だらけじゃないの、本当に洗ったの?きれいに洗ってきなさい!」
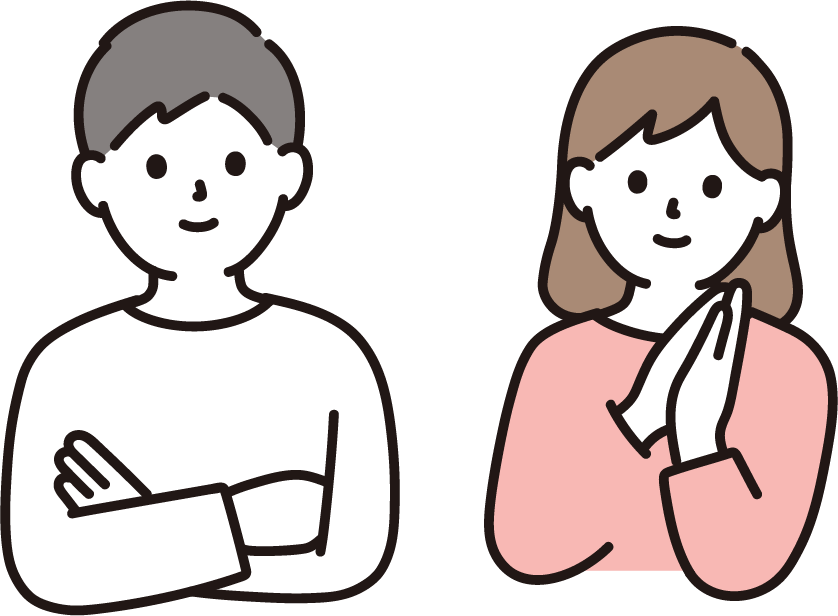 親B「ひとりで洗えたね。まだ指の間が汚れているね。もう一度、石けんをつけて、こういうふうに(実際に親がやってみせる)両手をゴシゴシ10回こすって水で流して、タオルで拭けたら、おやつにしようね。」
親B「ひとりで洗えたね。まだ指の間が汚れているね。もう一度、石けんをつけて、こういうふうに(実際に親がやってみせる)両手をゴシゴシ10回こすって水で流して、タオルで拭けたら、おやつにしようね。」
(こどもが手を洗ってきたら)
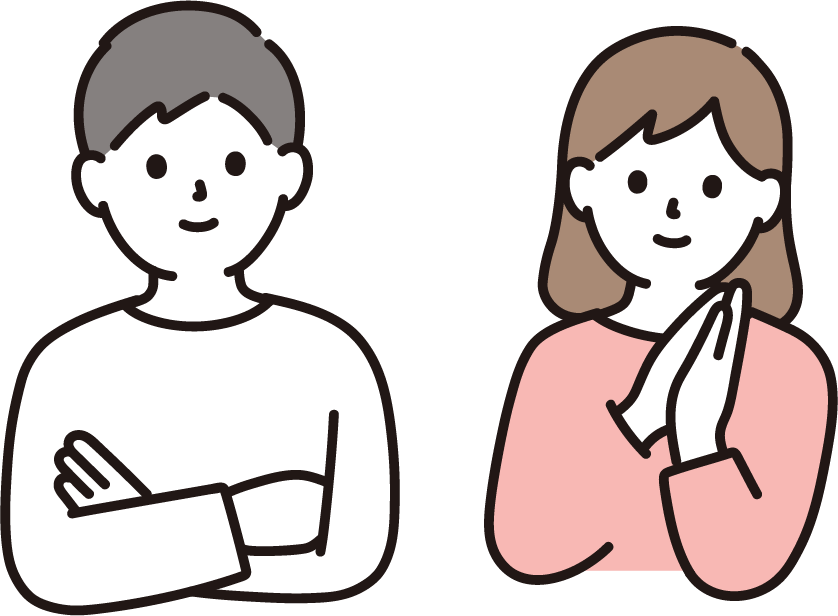 親B「きれいに洗えたね、気持ちいいね。さあ、おやつにしよう!」
親B「きれいに洗えたね、気持ちいいね。さあ、おやつにしよう!」
「きれいに」や「ちゃんと」というあいまいな表現を使うのではなく、わかりやすい言葉を使って手洗いの方法を伝えつつ、親が実際に手洗いのお手本を見せながら教えましょう。
「今日はお葬式だから、いい子でいてね」そう言われたこどもは、一生懸命、ニコニコしていました。その結果、周りから注意され、親からも「何笑ってるの!」と叱られてしまいました。
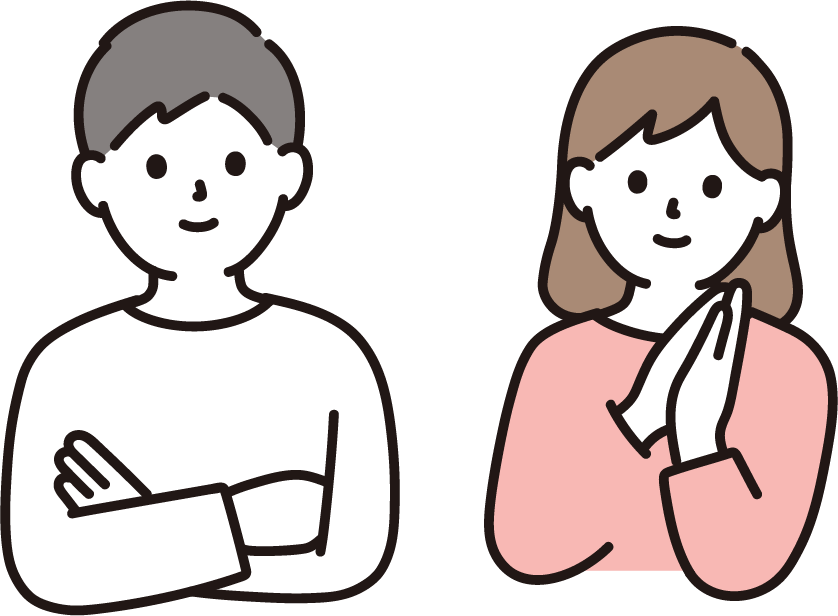 親「今日はお葬式だから、ママ(パパ)の隣の席に座って、静かにしていてね」
親「今日はお葬式だから、ママ(パパ)の隣の席に座って、静かにしていてね」
「いい子でいる」ことを、ニコニコしていることだと、こどもが理解している場合、あらゆる場面でニコニコしているかもしれません。「ちゃんとして」や「いい子にしてね」といった、あいまいな表現を使うのではなく、わかりやすい言葉で具体的に何をどうするかを伝えることが必要です。
 こども「ママー(パパー)、痛いよ~。」
こども「ママー(パパー)、痛いよ~。」
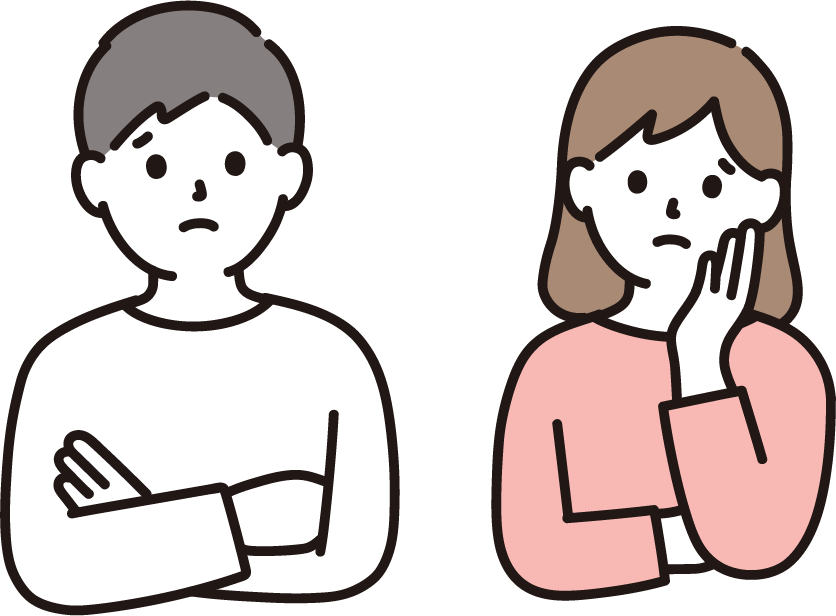 親A「転んだくらいで泣かないの!お店で走っちゃいけないって、いつも言ってるでしょ。何回言ったら分かるの!」
親A「転んだくらいで泣かないの!お店で走っちゃいけないって、いつも言ってるでしょ。何回言ったら分かるの!」
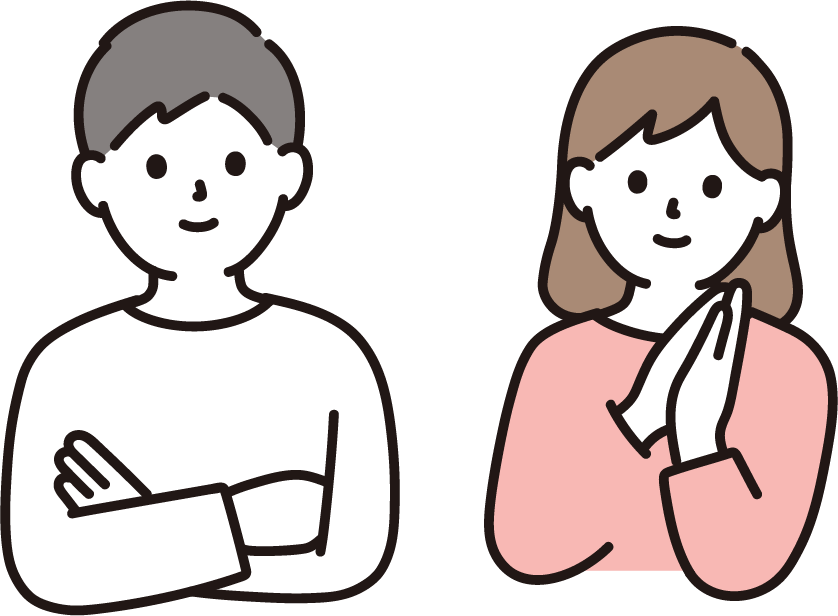 親B「転んじゃったの。痛かったね。大丈夫?お店ではママ(パパ)と一緒に歩いてお買い物しようね!」
親B「転んじゃったの。痛かったね。大丈夫?お店ではママ(パパ)と一緒に歩いてお買い物しようね!」
親が、こどもの言葉を頭から否定してしまったり、言葉の表面的な意味に反応してしまったりすると、こどもは親との会話を避けるようになりかねません。しかし、こどもの気持ちに寄り添い、共感的な言葉(例えば、「痛かったね」「悲しいね」「楽しいね」など)をかけると、こどもは親との会話を心地よいもの、楽しいものと感じるようになります。
 こども「ねー、ママ(パパ)、見て見て、きれいでしょう」
こども「ねー、ママ(パパ)、見て見て、きれいでしょう」
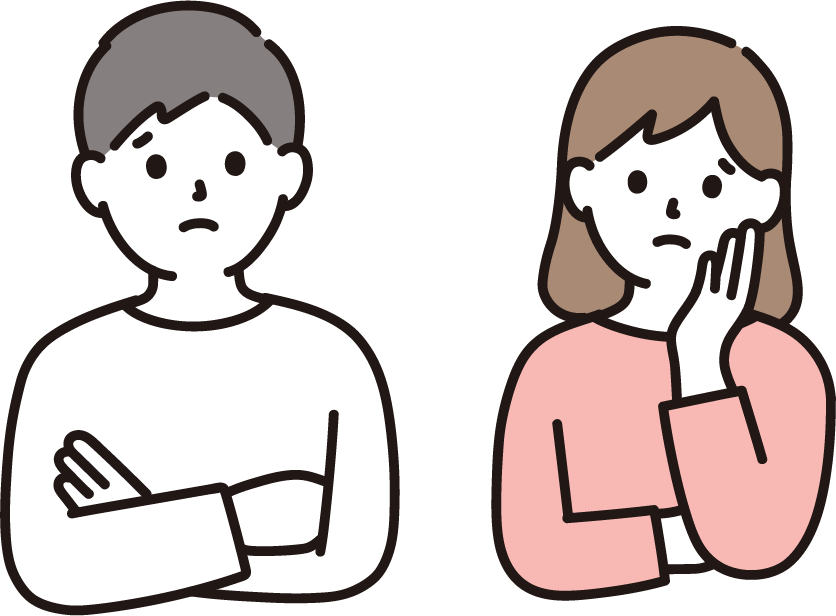 親A「塗り絵なんかやってないで、早く宿題しなさい!」
親A「塗り絵なんかやってないで、早く宿題しなさい!」
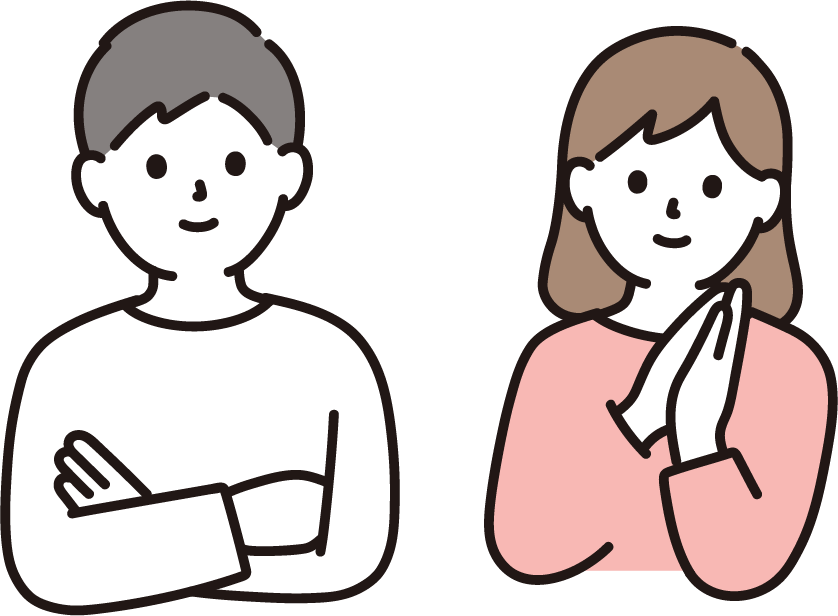 親B「うわー、いろんな色を使って、とってもきれいだね。少し休憩したら宿題しようね!」
親B「うわー、いろんな色を使って、とってもきれいだね。少し休憩したら宿題しようね!」
親が、こどもの言葉を頭から否定してしまったり、言葉の表面的な意味に反応してしまったりすると、こどもは親との会話を避けるようになりかねません。しかし、こどもの気持ちに寄り添い、共感的な言葉(例えば、「きれいだね」「楽しいね」「悲しいね」など)をかけると、こどもは親との会話を心地よいもの、楽しいものと感じるようになります。また、親にとっても、こどもとの会話を楽しいと感じられるようになるでしょう。
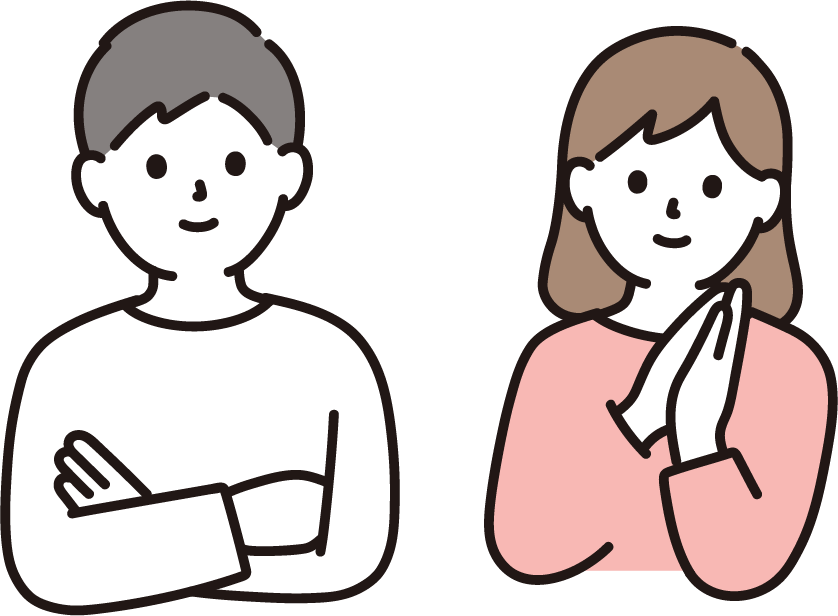 親「箸の使い方が上手になってきたね。こうやって持つと、もっと上手に使えるようになるよ。ちょっとやってみてごらん。」
親「箸の使い方が上手になってきたね。こうやって持つと、もっと上手に使えるようになるよ。ちょっとやってみてごらん。」
兄弟姉妹や、よその子と比べるのは、こどもの心を傷つけてしまう恐れがあります。例えば「・・・ちゃんはできるのに、どうして、あなたはできないの」、「お兄ちゃん(お姉ちゃん)なのに、どうして、妹(弟)よりも・・・できないの」という言い方は避けましょう。その子の中で、できていること、できたこと、上達したことをほめます。その上で改善できそうなことがあれば、「こうすると、もっとよくなるよ」と励ますと良いでしょう。
 こども「あっ!寝坊しちゃった。」
こども「あっ!寝坊しちゃった。」
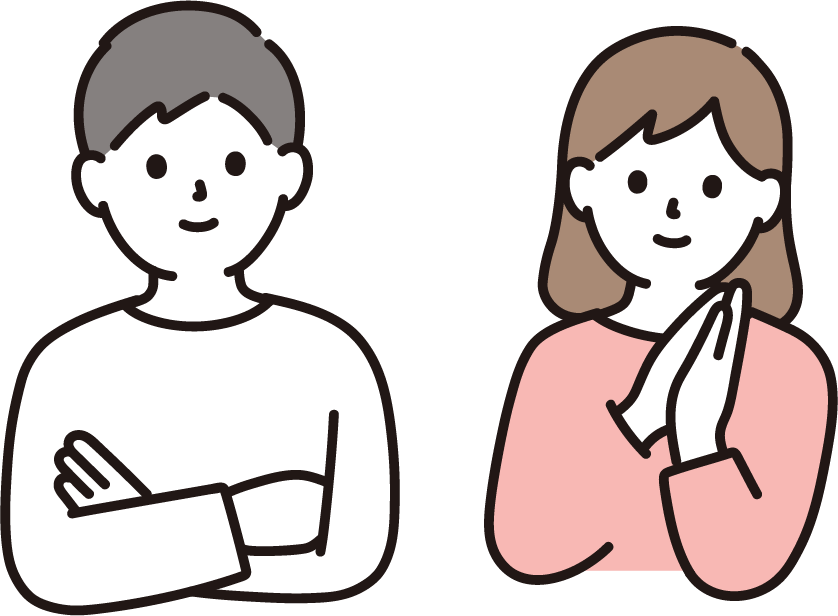 親「自分で時計をセットして起きようとしたね。そのやる気が大切だよ。また、やってみようね。」
親「自分で時計をセットして起きようとしたね。そのやる気が大切だよ。また、やってみようね。」
こどものできなかったところに着目するのではなく、自分からやろうとした気持ちや行動に着目して声をかけてあげることがポイントです。失敗しても次は頑張ろうという気持ちになれます。自分からやろうとした気持ちを認めることは、こどもの自己肯定感や自主性を育てる上でとても大切であり、良好な親子関係につながります。
 こども「パパ(ママ)、1番になれなかった。」
こども「パパ(ママ)、1番になれなかった。」
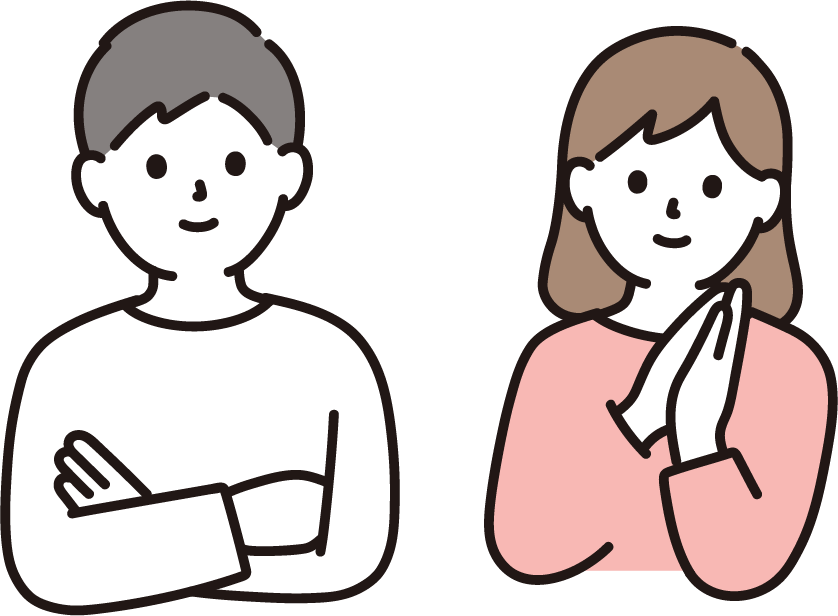 親「1番になれなかったのは残念だけど、パパ(ママ)との練習をよく頑張ったよね。」
親「1番になれなかったのは残念だけど、パパ(ママ)との練習をよく頑張ったよね。」
「結果」をほめるのは、できたことをほめることです。一方、「努力」をほめるのは結果にかかわらず、挑戦したことや頑張ったことをほめる(認める)ことです。親は結果だけを見て、こどもを評価してしまいがちですが、こどもが目標に向かってどのような行動をしたのかに着目して、具体的にほめてあげましょう。そうすることで、こどもの「もっと頑張ろう」というやる気を引き出すことにつながります。
 子ども「あっ、割れちゃった。」
子ども「あっ、割れちゃった。」
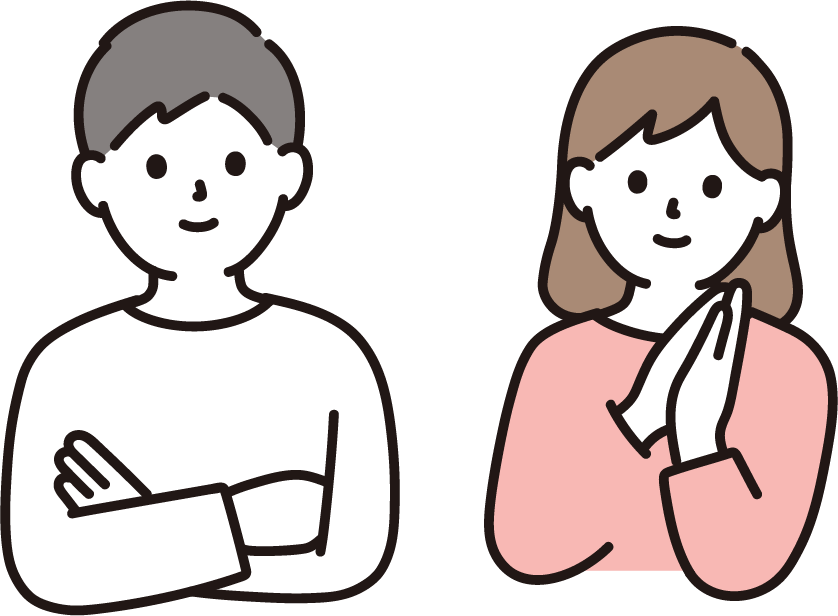 親『けがはない?大丈夫?お手伝いしてくれようとしたんだよね。ありがとう。』
親『けがはない?大丈夫?お手伝いしてくれようとしたんだよね。ありがとう。』
親は、結果だけを見て、こどもを評価したり、叱ってしまいがちです。
しかし、動機(こどもが自分からやろうとした気持ち)や、努力をほめることは、こどもの自己肯定感や自主性を育てる上でとても大切になります。
子育てにかかる親のストレスを軽減し、良好な親子関係づくりを目指す群馬県オリジナルの子育て講座プログラム「ほめて育てるコミュニケーション・トレーニング」(通称:ほめトレ)の内容を、楽しく分かりやすく学べる動画がありますので、ご視聴ください。
動画名:【群馬県】子育て講座「ほめトレ(幼児期編)」(27分50秒)<外部リンク>
https://youtu.be/XYJMt_bp-GY

(C) 2015 渋川市