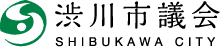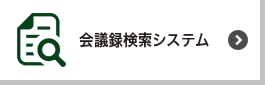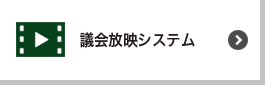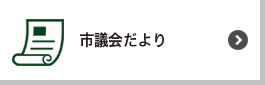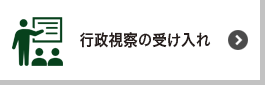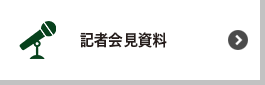市議会の概要
市議会の役割と権限
市議会の役割
私たちが暮らす渋川市を快適で住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが市政に参加し、実行していくことが理想ですが、多くの市民が一カ所に集まり話し合うことは困難です。そこで、市民の代表として市政を担う市議会議員と市長を選挙で選び、市民の声を市政に反映させています。
市議会議員は、議会において市民生活のさまざまな課題について審議し、どう処理すべきかを決定しています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。一方、市長は市議会が決めたことに基づいて実際に施策を実行します。このため、市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力しあい、市民生活の向上に努めています。
市議会の権限
議会が議案について可決、否決などの意思を決定することを「議決」といいます。議決には、予算や条例など団体としての渋川市の意思を決定するものと、意見書や決議など議会の機関意思を決定するものがあります。
議決の主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正、廃止
- 予算の決定、決算の認定
- 工事や物件の購入の契約
- 財産の処分
- 副市長、監査委員の選任や教育委員の任命の同意など、人事に関する事項
- その他法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。
これらの議決のほかに、市議会には調査、監査請求、意見書提出などを行う権限があります。
市議会のしくみ
議員定数と任期
渋川市議会議員の定数は18人で、任期は4年です。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会を代表して、議会に関する事務や本会議の議事の運営、対外的な議会の意思表明などを行います。
副議長は、議長が病気や事故などで不在のとき、または議長が欠けたときに議長の代わりにその職務を務めます。
会派
議会の意思は多数決で決まります。そこで、同じような意見や考えを持つ議員がグループをつくって活動すれば、自分たちの主張をより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」といいます。
本会議と委員会
本会議
本会議は議会及び市の最終意思を決定する会議です。提出された議案等について審議し、議決します。
全議員で構成され、議員定数の2分の1以上の出席により開くことができます。本会議には定例会と臨時会があり、いずれも市長が招集します。
定例会は規則により毎年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。
臨時会は、緊急の場合に特定の案件を示して臨時に招集されるもので、回数に制限はありません。
委員会
市行政は幅広く多岐にわたっており、それぞれ内容も専門的で複雑なため、多くの議案を本会議で一つずつ詳しく審議することは能率的ではありません。そこで、本会議のほかに、議案を専門的、能率的に審査する機関として委員会を設置しています。委員会は分野別に分かれており、それぞれの所管事項にかかる議案を審査します。
なお、委員会は議案を審査しますが、議決はできません。委員会で審査された議案は、委員会の審査結果をつけて再び本会議にかけられて、議決されます。
委員会は、常設の常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。
常任委員会
渋川市議会には「総務市民」、「経済建設」、「教育福祉」、「予算」の4つの常任委員会があります。
議員は少なくとも1つの常任委員会に所属することになっています。
|
委員会名 |
定数 |
所管事項 |
|---|---|---|
|
総務市民常任委員会 |
6人 |
総合戦略部、総務部、情報防災部、市民環境部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
|
経済建設常任委員会 |
6人 |
産業観光部、建設交通部、上下水道局及び農業委員会の所管に属する事項 |
|
教育福祉常任委員会 |
6人 |
福祉部、育都推進部及び教育部の所管に属する事項 |
|
予算常任委員会 |
17人 |
予算に関する事項 |
議会運営委員会
議長の諮問により、議会の会期、議案・請願等の取り扱いなど議会運営に関する事項について協議します。委員の定数は6人です。
特別委員会
特に重要な議案や案件等について調査する委員会です。本会議の議決によって設置され、案件の処理や調査が終了すると消滅します。
委員の定数も議決によって定められます。