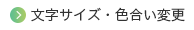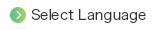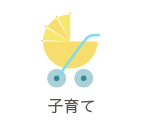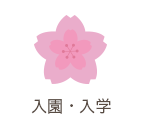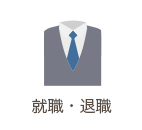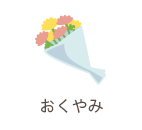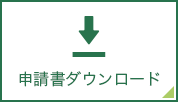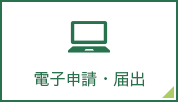令和6年度全国学校給食週間(1月24日〜30日)の取り組み紹介
全国学校給食週間とは
学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。
戦後、子どもたちの栄養状態を改善するために、昭和21年6月に米国のLARA(アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開されました。
同年12月24日に、東京都内の小学校でLARAからの給食用物資の贈呈式が行われたことから、この日を「学校給食感謝の日」と定めましたが、冬休みと重なってしまうため、1か月後の1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。
子どもたちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態に懸念される点が多く見られる今日、現在の学校給食は、子どもたちの心を豊かにし、食に関する正しい知識と望ましい食生活を身に付けるための健康教育の一環として、重要な役割を担っています。
学校給食週間においては、このような学校給食の意義や役割に関して、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を深め関心を高めるため、全国でさまざまな行事が行われます。
(参考:文部科学省ホームページ)
献立に込めた思い(栄養士コメント)
南部学校給食共同調理場
明治22年山形県の小学校でお弁当を持ってこられない子供たちにお昼を出したのが給食の始まりです。メニューは、おにぎり、焼き魚、漬物です。
南部調理場でもこの期間に始まりの給食や昔の給食、しぶきたメニューや近隣の給食などを取り入れました。
24日:昔の給食第一弾として給食では「ごはん、牛乳、鮭の塩焼き、すいとん、たくあんあえ、牛乳プリン」という献立にしました。牛乳プリンには脱脂粉乳が使われています。
27日:渋川北群馬のしぶきたメニューです。渋川北群馬でとれる野菜を使用してしぶきた丼を作ります。
28日:伊勢崎市でとれるニラをつかったニラメンチカツとごぼうは境地区でとれるごぼう「甘久郎」が有名です。伊勢崎市の給食でもごぼうの天ぷらやごぼうが入ったミネストローネが時期により出るそうです。
29日:前橋市の人気メニューtonton汁です。前橋は豚肉の町です。名物料理を考案しようと市内の料理人11人で考案されたものです。群馬県産の豚肉、こんにゃくやきのこや野菜、油揚げやすいとんが入り、しめじはバターソテーして入れます。味は味噌味です。
前回とても人気でまた食べたいとのリクエストがありましたので入れてみました。
30日:昔の給食第二弾です。昭和23年頃出ていたカレーシチュウです。カレーではなくシチューでもなくパンに合うカレーシチュウです。脱脂粉乳が入っていてまろやかなカレー味のシチュウといった感じなります。ジャムをつけましたが、コッペパンをちぎってカレーシチュウをつけて食べてもらいたいです。
北部学校給食共同調理場
全国学校給食週間(1月24日~30日)の献立は、明治22年に山形県鶴岡市の小学校で給食が始まった頃の献立の「焼き魚、漬物」や戦後によく食べられていた「すいとん」、昭和22年~25年頃「コッペパン、シチュー」、昭和40年~50年代の給食「米飯給食」にちなんだ献立とし、給食の歴史を振り返ることができるような給食を提供しました。
日頃、何気なく食べている給食について、給食の始まったきっかけや給食の移り変わりを知り、給食や食について関心をもってもらうきっかけとなってもらいたいという思いで献立を作成しました。
東部学校給食共同調理場
学校給食週間の献立は、給食が始まった頃や、昔から現在まで続いている献立を提供することで、歴史を振り返ることができるようにしました。さらに、渋川北群馬郡で生産されている農畜産物をつかった献立や、渋川市の姉妹都市「イタリア国フォリーニョ市・アバノテルメ市」にちなんでイタリアの料理について提供することで、給食から渋川のことを学ぶことができるようにしました。
食に関する指導の紹介
南部学校給食共同調理場
学校給食給食の歴史について紙芝居を5.6年生に行いました。給食の始まりや、戦争で一時中断したこと、戦後の食糧難から各国の支援物資で給食を再開できたことなどを給食の移り変わりと共に紹介しました。現在の給食では、みんなで楽しく食べるためのマナーを身につけたり、住んでいる地域ではどんな食材がとれるかということが給食を通して学ぶことができるようになりました。栄養を満たすだけでなく、季節の行事食や各地の郷土料理などを提供し、「生きた教材」として食育の大切な働きをしていることを伝えました。


北部学校給食共同調理場
全国学校給食週間についてと、学校給食の歴史についての紙芝居を小学校4年生に行いました。給食がはじまったきっかけや、日本で最初の学校給食、戦争で一時中断し、再開されたころの子供たちの様子、学校給食が戦後、再びスタートできたことなど給食の歴史について伝えることで、給食について考えてもらう機会としました。
時代の流れとともに変化してきた学校給食ですが、いつの時代も子どもたちのことを大切に思う気持ちで作られていることを伝え、食べ物の大切さや給食が届くまでにたくさんの人たちが関わっていることを伝えました。

東部学校給食共同調理場
3年生と5年生を対象に、学校給食の歴史や提供した献立についての話をクイズ形式で行いました。毎年、全国学校給食週間にあわせて学校給食の歴史の話をしているので、今年はクイズ形式で行うことで、楽しみながら内容を思い出してもらえるよう工夫しました。東部調理場の人気メニューについてのクイズなども盛り込み、より給食が身近に感じられるようにしました。また、すべての受配校に学校給食の歴史についての掲示資料を配付し、給食時間の放送や献立表でも伝えました。