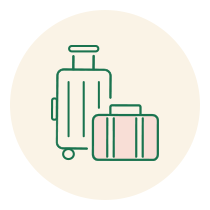徳冨蘆花記念文学館

お知らせ
休館日について
徳冨蘆花記念文学館は、令和6年4月1日(月曜日)から、毎週金曜日が休館日となります。
また、年末年始は12月29日から翌1月3日までが休館日となります。
2月の文学館
2月8日の日曜日、全国的に雪模様だったこの日、伊香保にも本格的に雪が積もりました。
この時期は、いつ雪が降るかわかりませんので、万全の雪対策でお越しください。

(庭園前)

(記念館前)

(終焉の間からの景色)
(令和8年2月9日撮影)
蘆花先生の作品のひとつである「自然と人生」の中に「自然に対する五分時」という短編集があります。今回は、朝日と富士山を描写した「此頃の富士の曙」を紹介します。明け方の綺麗な色合いを美しい文章で表現しています。景色や色合いを想像しながらお楽しみください。
心あらん人に見せたきは此頃の富士の曙。
午前六時過、試みに逗子の濱に立つて望め。眼前には水蒸気渦まく相模灘を見む。灘の果てには、水平線に沿ふてほの闇き藍色を見む。若し其北端に同じ藍色の富士を見ずば、諸君恐らくは足柄、箱根、伊豆の連山の其藍色一抹の中に潜むを知らざる可し。
海も山も未だ睡れるなり。
唯一抹、薔薇色(しょうびいろ)の光あり。富士の巓をさる弓杖ばかりにして、横に棚引く。寒を忍びて、暫く立ちて見よ。諸君は其薔薇色の光の、一秒一秒富士の巓に向つて這ひ下るを認む可し。丈、五尺、三尺、尺、而して寸。
富士は今睡より醒めんとすなり。
今醒めぬ。見よ、頂の東の一角、薔薇色(ばらいろ)になりしを。
請ふ瞬かずして見よ。今富士の巓にかかりし紅霞は、見るが内に富士の暁闇を追ひ下ろし行くなり。一分――二分、――肩、――胸。見よ、天邊に立つ珊瑚の富士を。桃色に匂ふ雪の膚、山は透き徹らむとすなり。
富士には薄紅に醒めぬ。請ふ眼を下に移せ。紅霞は已に最も北なる大山の頭にかかりぬ。早や足柄に及びぬ。箱根に移りぬ。闇を追ひ行く曙の足の迅さを。紅追ひ藍奔りて、伊豆の連山、已に桃色に染まりぬ。
紅なる曙の足、伊豆山脈の南端天城山を越ゆる時は、請ふ眼を回へして富士の下を望め。紫匂ふ江の島のあたりに、忽然として二三の金帆の閃くを見む。
海已に醒めたるなり。
諸君若し倦まずして猶たたずまば、やがて江の島に對ふ腰越の岬嚇として醒むるを見む。次で小坪の岬に及ぶを見む。更に立ちて、諸君が影の長く前に落つる頃に到らば、相模灘の水蒸気漸く収まりて海光一碧、鏡の如くなるを見む。此時、眼を挙げて見よ。群山紅褪せて、空は卵黄より上りて極めて薄き普魯士亜藍色(ぷるしああゐ)となり、白雪の富士高く晴空に寄るむを見む。
ああ心あらん人に見せたきは此頃の富士の曙。
令和7年度企画展「絵双六と絵はがき展」
1月4日(日曜日)から2月26日(木曜日)までの期間で、「絵双六と絵はがき展」を開催しています。
本展では、明治から昭和にかけて発売された「絵はがき」や、婦人雑誌等の附録でお正月に家族そろって楽しんだ「絵双六」を多数展示しています。


令和7年度企画展「紙芝居展」
11月5日(水曜日)から12月25日(木曜日)までの期間で、「紙芝居展」と題しまして、群馬県立土屋文明記念文学館の移動展を開催しています。
紙芝居は、昭和5年頃に「黄金バット」や「鞍馬天狗」などの街頭紙芝居として登場した日本特有の文化財です。本展では、紙芝居のルーツをたどり、最初期の街頭紙芝居から教育紙芝居などさまざまな紙芝居とその歴史を紹介します。

11月に入り、だいぶ寒くなってきました。撮影日の11月3日は、日中でも10℃を下回る気温でした。伊香保へお越しの際は、調節できる服装でお越しください。

(庭園前)

(記念館前)

(終焉の間からの景色)
蘆花先生の作品のひとつである「自然と人生」の中に「自然に対する五分時」という短編集があります。今回は、今の時期と同じ11月に記した「利根の秋暁」を紹介します。蘆花先生が茨城県神栖市息栖で過ごした、明け方の小見川の風景を綺麗な文章で描写しています。景色や色合いを想像しながらお楽しみください。
先年秋十一月の初旬、利根の左岸の息栖と云ふ所に泊まつた。此處は利根の本流が北利根北浦の末流と落合ふて來るので、川幅が濶く、對岸(むかふ)の小見川迄は小一里もあらふ。宿は値ぐ水邊にあつて、夜中に眼を醒ますと、櫓の音が軋々(ぎいぎい)枕頭に聞へる。
黎明(あけがた)に起きて、宿の者は未だ寝て居るので、窃と戸を明けて、河邊に出ると、其處に薪がつむである。霜を拂つて、腰かけた。未だほの闇い、空も河面も茫として鉛色(えんしよく)であつた。直ぐ裏の方の闇い小屋の中で、鶏が勇ましく暁を告げると、餘程經て川向ふの小見川の方から、さも微かな鶏の音が聞へた。大河を隔てゝ呼びかはす此鶏聲は、實に宜い、チエルシアの賢とコンコルドの哲とは實に斯くの如く大西洋を隔てゝ呼びかはしたのであらふ。抑も亦た自分が眼には、暁は此の兩岸の鶏聲の間から河面に湧き上がつて來る様に思はれた。暫くすると、小見川の方の空がぼうつと薔薇色になつて來た。と見ると、河面も薄紅を流して、ほやりほやり水蒸氣が見へて來た。實に迅い、瞬きをする間もないのである。夜は川下の方へ流れて、曙の光は四邊に満ち満ちて居る。鶏は猶鳴きつゞける。空と水の薔薇色が少し褪ふ。忽ち晃々(きらきら)と眼ばゆき光が水に流れる。ふり顧り見れば、朝日は杲々(こうこう)として今息栖の宮の森の梢を離れたのである。其の梢離るゝ烏一羽、朝日を負ふて、宛ながら暁を告げ渡る神使の如く、凜とした朝(あした)の大氣に羽搏つて、小見川の方へ飛んで行く。小見川は未だ碧々とした朝霧に眠つて居る。
對岸(むかふ)は未だ眠つて居るが、此方の村は最早さめた。背後の芧舎から煙が立上る。今柵を出た家鴨は足跡を霜に印て、刮々(くわつくわつ)呼びながら、朝日を碎いて水に飛び込む。川楊の枝に小鳥が囀へづる。今起きて來た村人が、白い息を吹き吹き川に下りて、河水を掬(むす)んで嗽(くちそゝ)ぎ、顔を洗ひ、それから遙かに筑波の方へ向いて、掌を合はして拝むで居る。
あゝ實に好い拝殿、と自分は思つた。
10月の文学館
朝晩の冷え込みは、すっかり秋めいてきました。
文学館からの景色も秋の訪れを感じるものとなってきています。

(庭園前)

(記念館前)


(記念館前のホトトギスが綺麗に咲いています。)

(終焉の間からの景色)
(令和7年10月8日撮影)
蘆花先生の作品のひとつである「自然と人生」、その中には蘆花先生が自然と共に過ごした景色を綺麗な文章で表した短編集があります。
今回はちょうど今の時期と同じ10月の栃木県塩原温泉郷付近の景色を記した「空山流水」を紹介します。
或年の秋、十月の末であつた、自分は鹽原箒川の支流鹿股川の畔の石に腰かけて居た。前夜凩が烈しく吹いて、紅葉は大抵散つてしまつて、川床は殆んど眞紅になつて居た。右も左も見上ぐる程の峰が細長く青空を限つて、空にも川が流れて居るかと思はれた。秋末の事で、水は痩せ、涸れに、涸れて、所謂全石の川床の眞中を流れて行く。川床は峰と峰との谷間をくねつて、先下りになつて居るから、遠くまで流の末が見へる。恰川の末に一高峰が立ち塞がつて、遠くから見ると川は其峰に吸ひ込まれるかの様に思はれ、又山が、「此處に居なさい、里に出て何になる、居なさい、居なさい」と水の流を抱き止める様にも思はれる。
併し水は底の石を流ひ、紅葉の柵を潜つて、歌ひながら流れて行く。石に腰かけて、聞いて居ると、其音!松風、人無くして鳴る琴の音、何に譬へて宜からう?身は石上に坐しながら、心は流水の行末を追つて、遠く、遠く、遠く--あゝまだ仄かに聞こへる。
今でも半夜夢醒めて、心澄む折々は、何處かに遠く遠く此音が聞へるのである。
お知らせのバックナンバーについて
最新のお知らせを、上記に表示しています。これまでの記事は、下記のリンクからご確認ください。
徳冨蘆花記念文学館からのお知らせのバックナンバーは、こちらをクリックしてください。
施設の概要
小説「不如帰(ほととぎす)」で有名な明治の文豪、徳冨蘆花は自然豊かな伊香保を気に入り、何度も足を運びました。徳冨蘆花記念文学館では、蘆花が定宿としていた旅館の離れを移築・復元し、記念館として公開しています。
ほかに、当時の「写真や書簡、遺品、文学作品など蘆花に関する様々な資料を揃えた展示館もあり、豊富な展示資料からは蘆花の生い立ちや、時代背景についても触れることができます。
利用案内
開館時間
- 8時30分から17時00分(入館は16時30分まで)
観覧料
- 一般大人350円、小中高校生200円
団体(20名以上)大人300円、小中高校生150円
ただし、障がい者手帳等をお持ちの方と付き添いの方1名まで無料です。
休館日
- 毎週金曜日
- 12月29日から翌1月3日まで
写真紹介

常設展示室

記念館玄関

蘆花終えんの部屋
イベント情報
企画展
錦絵展
- 日程:令和7年5月5日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで
浮世絵展
- 日程:令和7年7月5日(土曜日)から8月31日(日曜日)まで
夢見る女性誌展
- 日程:令和7年9月6日(土曜日)から10月30日(木曜日)まで
紙芝居展
- 日程:令和7年11月5日(水曜日)から12月25日(木曜日)まで
絵双六と絵はがき展
- 日程:令和8年1月4日(日曜日)から2月26日(木曜日)まで
渋川の碑めぐり展
- 日程:令和8年3月5日(木曜日)から4月30日(木曜日)まで
追悼お茶会
蘆花を偲び、月命日に「静翠会」による追悼茶会を開催します。
日程
- 令和7年5月18日(日曜日)10時から15時まで
- 令和8年1月18日(日曜日)10時から15時まで
金額
- お一人さま500円
アクセス
バス
「伊香保バスターミナル」下車徒歩10分[該当バス路線は下のとおり]
- 渋川駅~伊香保温泉線(関越交通バス)
- 伊香保~榛名湖線(群馬バス)
「伊香保案内所」下車徒歩3分[該当バス路線は下のとおり]
- 渋川駅~水沢経由伊香保線(群馬バス)
- 伊香保~高崎線(群馬バス)
- 水沢シャトルバス(群馬バス)
「伊香保石段街」下車徒歩3分[該当バス路線は下のとおり]
- 渋川駅~伊香保温泉線(関越交通バス)
- 東京・新宿~伊香保・草津温泉線(JRバス)
経路検索にはGunMaaSが便利です
目的地までの路線バスや鉄道の経路検索に、スマートフォン専用サービス「GunMaaS」をご活用ください。
GunMaaS(https://lp.g3m.jp/)
お問い合わせ先
徳冨蘆花記念文学館
所在地 群馬県渋川市伊香保町伊香保614番地8
電話番号 0279-72-2237
ファクス番号 0279-72-2237(電話番号と共通)