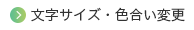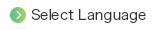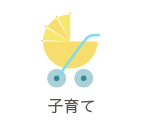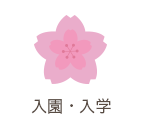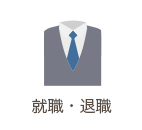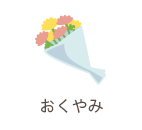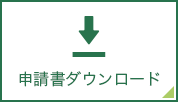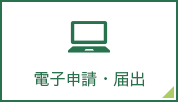後期高齢者医療保険料
75歳以上の人と、一定の障がいのある65歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料を納めていただきます。
保険料算出の基準となる保険料率(均等割額及び所得割率)は、高齢者の医療の確保に関する法律によって2年ごとに見直され、群馬県後期高齢者医療広域連合が決定し、群馬県内で均一となります。
保険料の計算方法や保険料率改定の詳細に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の納め方について
年金から差し引かれる「特別徴収」と、口座振替や納付書で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。
年金から差し引かれる人(特別徴収)
対象者
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上の人
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない人
- 介護保険料が特別徴収されている人
納め方
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。条件を満たした人でも、資格を取得したばかりの人や保険料額が変更になった場合には、特別徴収とならない場合があります。
仮徴収(4月、6月、8月)
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます。(前年度2月の特別徴収額と同額を差し引くか、前年度年間保険料の6分の1を各月から差し引きます。)
ただし、4月、6月、8月の仮徴収額と10月、12月、2月の本徴収額の金額の差が一定額以上あると見込まれた人は、特別徴収額ができるだけ均等になるように6月と8月の仮徴収額を変更します。(仮徴収額の平準化)
本徴収(10月、12月、2月)
確定した年間保険料額から、仮徴収額分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。
特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方
金融機関で口座振替の手続き後、市の窓口で申請してください。ただし、口座振替で確実に保険料の納付ができる場合に限りますので、口座振替不能となった際は、特別徴収が再開されます。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから口座振替に切り替るまで数ヶ月ほどお時間がかかります。
納付書で納める人(普通徴収)
対象者
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の人
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える人
- 介護保険料が普通徴収の人
- 資格を取得したばかりの人
- 他の市区町村から転入してきた人
納め方
市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めていただきます。
納期
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です。(納期は市町村によって異なります。)
口座振替をご利用ください
普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。