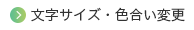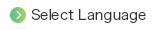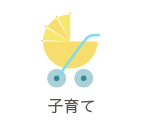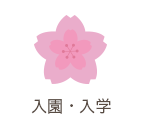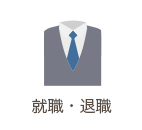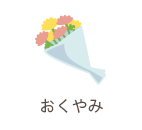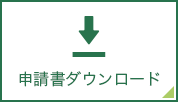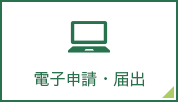国保からの給付
国保では病気やケガをしても安心して医療が受けられるよう、次のような給付をおこなっています。
|
内訳 |
こんなとき |
手続きおよび必要なもの |
給付 |
|---|---|---|---|
|
療養の給付 |
病気やケガでお医者さんにかかったとき。 |
マイナ保険証又は資格確認書を病院や医院の窓口へ提出してください。 交通事故の場合は、必ず市役所へ届出してください。 |
医療費の7割(一般、退職者とも)ただし、義務教育就学前は8割、70歳以上は(補足)8割または7割 |
|
高額療養費 |
医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、預金通帳 |
詳しくは高額療養費へ |
|
療養費 |
やむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書を使わないで治療を受け、自費で医療費を支払ったとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、診療内容の明細書(レセプトなど)、預金通帳 |
書類を添えて、申請書とともに国保の窓口へ提出してください。審査後に医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は(補足)8割または7割)の払い戻しが受けられます。 (ただし、海外での受診の場合、日本国内の診療料金を標準とします。また、日本語の翻訳が必要です。) 詳しくは療養費へ |
| 療養費 |
医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、医師の同意書、診療内容の明細、預金通帳 |
|
| 療養費 |
施術などの際に、他人の生血を輸血したとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、医師の診断書、預金通帳 |
|
| 療養費 |
治療上必要があってコルセット等を装着したとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、医師の同意書、預金通帳 |
|
| 療養費 |
海外渡航中に受診し、自費で医療費を支払ったとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、診療内容の明細・領収明細書(翻訳されたもの)、領収書の原本、診療を受けた方のパスポート、預金通帳 |
|
|
移送費 |
重病人の入院や治療に必要な転院などの移送にかかった費用で、国保が必要であると認めたとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、領収書、医師の同意書、預金通帳 |
書類を添えて、申請書とともに国保の窓口へ提出してください。審査後に医療費の払い戻しが受けられます。 詳しくは移送費へ |
|
入院時食事療養費 |
病気やケガで病院や医院等に入院して食事をしたとき。ただし標準的な食事代については、自己負担していただきます。 |
マイナ保険証又は資格確認書及び標準負担額減額認定証を病院や医院の窓口へ提出してください。 |
詳しくは入院食事療養費へ |
|
生活療養費 |
65歳以上の人が療養病床に入院する場合、平均的な食費や光熱水費は自己負担となります。 |
マイナ保険証又は資格確認書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を病院や医院の窓口へ提出してください。 |
詳しくは生活療養費へ |
|
訪問看護療養費 |
脳卒中などで家庭で寝たきりの人に対してお医者さんの指示にもとづいて、訪問看護ステーションから看護師さんや保健師さんが訪問し、お世話したとき。 |
マイナ保険証又は資格確認書を病院や医院の窓口へ提出してください。 |
療養の給付と同じ。 |
|
その他 |
被保険者が出産したとき。 |
直接支払い制度を利用しない場合 保険資格のわかるもの(資格確認書等)、母子健康手帳、預金通帳、領収書、明細書、産科医療補償制度の適用の有無が分かる書類、直接支払い制度を利用しないことが分かる書類、(死産の場合)死産届のコピー |
出産育児一時金50万円 産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円 詳しくは出産育児一時金へ |
| その他 |
被保険者が亡くなったとき。 |
保険資格のわかるもの(資格確認書等)、喪主が分かるもの(領収書や会葬礼状など)、預金通帳 |
葬祭費5万円 詳しくは葬祭費へ |
マイナ保険証又は資格確認書を窓口に提示又は電子的確認をすれば、医療費の一部を負担するだけで、医療機関等にかかることができます。
| 割合 |
0歳から 義務教育就学前 |
義務教育就学後から 69歳 |
70歳から74歳 |
|---|---|---|---|
|
療養の給付 (国保負担割合) |
8割 | 7割 |
8割 (現役並み所得の人7割) |
| 自己負担割合 | 2割 | 3割 |
(補足)2割 (現役並み所得の人3割) |
入院時の食事代 入院時食事療養費の支給
入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額自己負担することになります。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
- A 一般(下記以外の人) 510円
- B 住民税非課税世帯の人(70歳以上は世帯主と国保加入者が住民税非課税の人)から90日 240円
- B 住民税非課税世帯の人(70歳以上は世帯主と国保加入者が住民税非課税の人)91日から 190円
- C 世帯主と国保加入者が非課税で、収入から必要経費・控除を差し引くと所得がなくなる世帯に属する70歳以上の人 110円
(補足)B・Cに該当する人は保険年金課または各行政センターへ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付手続きに必要なもの)
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- 入院期間が分かる領収証や明細書(Bで入院が過去1年間で91日以上の場合)
療養病床に入院する場合 生活療養費の支給
65歳以上の人が療養病床に入院する場合、平均的な食費や光熱水費は自己負担することになります。
| 区分 |
標準負担額 居住費(1日分) |
標準負担額 食費(1食分) |
|
|---|---|---|---|
|
(1)一般、現役並み所得者(下記以外の人) |
370円 |
510円または470円(注意1) |
|
|
(2)世帯主と国保加入者が住民税非課税の人 |
370円 |
240円 |
|
|
(3)世帯主と国保加入者が住民税非課税で、収入から必要経費・控除を差し引くと、所得がなくなる世帯に属する人で、年金収入が80万円以下などの場合 |
370円 |
140円または110円(注意2) |
|
(注意1)医療機関によって金額が異なります。
(注意2)医療の必要性の高い人(指定難病患者など)が対象です。
(補足)(2)、(3)に該当する人は保険年金課または各行政センターへ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。
(2)に該当する人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合1食190円に減額されますので、入院日数を確認できるもの(領収書など)を持参して申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付手続きに必要なもの)
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
在宅で療養するとき 訪問看護療養費の支給
訪問看護などのサービスを、かかった費用の一部を支払うだけで利用することができます。
- 在宅で療養する人が医師の指導のもとで訪問看護ステーションを利用するときは、窓口に保険資格のわかるもの(資格確認書等)を提示するか、窓口で電子的確認を受けてください。かかった費用の3割の自己負担で訪問看護サービスが受けられます。
交通事故にあったら、示談の前に届け出を
交通事故などの第3者(加害者)によるケガや病気のときでも、国保で治療を受けることができます。ただし、国保で負担した治療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。ですから、国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。 そのため、交通事故などにより国保で治療を受けたときは、必ず届出をしてください。
交通事故に遭ったときの注意点
- 警察に届ける。
- 国保に届ける。
- 加害者から治療費を受けとった場合には国保は使えません。示談はくれぐれも慎重に。
医療費のはなし
医療費が毎年1兆円近く増え続けているのを知っていますか。
医療費が増え続けると
このまま医療費が増え続けると、国保の財政がどんどん悪化して、これまで紹介してきたような各種の給付ができなくなってしまいます。
保険税の値上げなどに頼らずに国保を健全に運営していくには、わたしたち一人ひとりが医療費の削減につとめる必要があります。
医療費を減らすには
これ以上、医療費を増やさないよう、次のことを実行しましょう。
- ふだんから健康づくりに励みましょう
- 病気の早期発見・早期治療を心がけましょう
- かかりつけ医をもちましょう
- かかりつけ薬局をもち、薬の正しい使用を心がけましょう