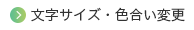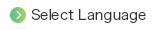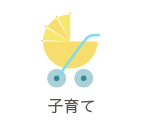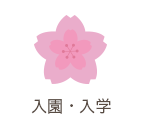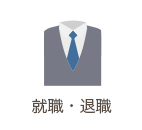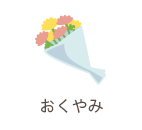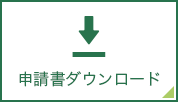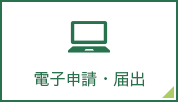福祉医療制度と手続き
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
福祉医療費受給資格の申請について
福祉医療制度は、別表の資格要件に該当し、受給資格者証を持っている人が加入する健康保険で医療機関等を受診したとき、保険診療による自己負担分を市町村と県が福祉医療費として助成する制度です。
まだ手続きをしていない人で、別表の資格要件に該当する人は受給資格者証が交付されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、保険年金課または各行政センターの窓口へ申請してください。
| 区分 | 資格要件 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 子ども |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人 |
|
| 重度心身障害者(児)
(後期高齢者医療被保険者を除く) |
(いずれも世帯全員の前年所得の申告が済んでいる人) |
|
|
精神通院医療者 (後期高齢者医療被保険者を除く) |
障害者総合支援法施行令第1条の2第3号が適用されている人 (注意)ただし、定められた医療機関・薬局に限る |
|
|
高齢重度障害者 (後期高齢者医療被保険者) |
(いずれも世帯全員の前年所得の申告が済んでいる人) |
|
| ひとり親家庭等 |
(いずれも前年所得の申告が済んでいる人) |
|
- 申請書は、こちらからダウンロードすることができます。
(補足)受給資格認定申請(こども)は電子申請が可能です。
- 前住所地の交付状況証明書(県内転入者のみ)も必要になります。
- 障害年金1級程度の障害の状態にあると思われる方で、障害年金を受給できない方でも、福祉医療の認定を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
- 婚姻(事実婚を含む)等により、「ひとり親家庭等」の資格要件を満たさなくなった場合は受給資格がなくなりますので、保険年金課または各行政センターの窓口へ申し出てください。
- 重度心身障害者(児)・高齢重度障害者で転入してきた方の場合、1月2日以降に転入した世帯全員分の所得・課税証明書が必要になります。
(補足)マイナンバーを利用することに同意していただくと、所得課税証明書の添付を省略することができます。
重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の福祉医療費受給資格の所得制限について(令和5年8月から)
これまで、資格要件を満たす重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の人については、所得に関わらず助成の対象としてきましたが、福祉医療制度を安定的かつ長期的に行っていくため、令和5年8月から所得制限が設けられました。
前年中の所得が下の表に該当する場合は、8月から翌年7月までの重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の福祉医療費を受給できなくなります。
詳細については、保険年金課まで問い合わせてください。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者又は扶養義務者の所得額 | ||
| 所得制限基準額 | 収入額の目安 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 | |
|
0人 |
3,661,000 | 約5,252,000 | 6,287,000 | 約8,319,000 |
| 1人 | 4,041,000 | 約5,728,000 | 6,536,000 | 約8,586,000 |
| 2人 | 4,421,000 | 約6,204,000 | 6,749,000 | 約8,799,000 |
|
3人 |
4,801,000 | 約6,668,000 | 6,962,000 | 約9,012,000 |
(補足)対象となる所得は、給与所得、退職所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金等)などです。
(補足)受給者本人の所得が基準額を下回っていても、配偶者などに基準額以上の所得がある場合は、対象外です。
(補足)所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
(補足)扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
(補足)収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。
(補足)昨年度所得制限により対象外となった方も今年度の所得によっては対象となる場合があります。
(補足)すでに受給している方でも、未申告などにより前年の所得が確認できない場合は、資格の更新ができません。
住所や登録事項に変更があったときなどは届出が必要です。
つぎのようなときは、手続きに必要なものを持参のうえ、保険年金課または各行政センターの窓口へ届出をしてください。
| 区分 | こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 資格変更 | 加入している健康保険が変わったとき | 受給資格者証
保険資格のわかるもの(資格確認書等) |
| 市内で住所が変わったとき | 受給資格者証 | |
| 氏名、世帯主が変わったとき | 受給資格者証 | |
| 資格喪失 | 市外へ引っ越すとき | 受給資格者証 |
| 死亡したとき | 受給資格者証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 受給資格者証
保護開始決定通知書 |
|
| その他 | 受給資格者証を紛失・破損したとき | 受給資格者証(破損の場合) |
| 障害者手帳・療育手帳・障害年金などの記載事項が変更になったとき | 受給資格者証
身体障害者手帳など |
|
| 交通事故でケガをしたとき | 受給資格者証
保険資格のわかるもの(資格確認書等) 交通事故証明書など |
福祉医療費受給資格の喪失について
以下のとき、福祉医療費の受給資格は喪失され、資格喪失後の医療費は自己負担となります。
(1)年齢到達による資格喪失
年齢到達によって、以下の人は福祉医療費受給資格を喪失します。
- 子ども・・・18歳に達した日以後最初の3月31日
- ひとり親・・・子が18歳に達した日以後最初の3月31日
- 精神通院医療・・・75歳の誕生日または後期高齢者医療制度に加入した日
場合によっては、別の福祉医療費受給資格を受けられますので、別ページ(福祉医療制度と手続き)の資格要件を確認してください。
(2)身体障害者手帳等の有効期限経過による資格喪失
身体障害者手帳・療育手帳等に有効期限がある人は、福祉医療費受給資格にも有効期限があります。
福祉医療費の受給資格を更新するためには、身体障害者手帳等の更新を済ませた後、福祉医療費受給資格者証の有効期限を迎える前に更新の申請をしてください。
(有効期限経過後に申請した場合、新規の申請となり、受給資格を得られるのは申請日以降となります。)
(3)転出
渋川市を転出されると、転出日から福祉医療費の受給資格はなくなります。
(4)前年所得が基準額を超えたとき(重度心身障害者・高齢重度障害者)
(5)その他資格要件を満たさなくなったとき
資格喪失後は福祉医療費受給資格者証を必ずご返却ください。
資格喪失後に使用した場合、医療費を返還していただきます。
入院時の食事代について
重度心身障害者又は高齢重度障害者の資格をお持ちの人は、入院時食事療養標準負担額について所得に応じて自己負担が発生します
入院時食事療養標準負担額(入院時の食費にかかる自己負担分)については、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「標準負担額減額認定証」という。)を医療機関に提示又は電子的確認をした場合のみ、無料となります。
子ども又はひとり親家庭等の資格をお持ちの人は、入院時の食費についても無料になります。
標準負担額減額認定証
標準負担額減額認定証は、入院時の食事に係る自己負担を所得に応じて減額するための認定証で、住民税非課税世帯等に対して保険者(健康保険組合等)が申請により交付します。
標準負担額減額認定証の交付が受けられる人は、事前に申請してください。住民税非課税世帯であっても標準負担額減額認定証の提示又は電子的確認がないと食費が無料にならないのでご注意ください。
なお、国民健康保険又は後期高齢者医療に加入している人は、保険年金課又は各行政センターで申請できますので保険資格のわかるもの(資格確認書等)をご持参ください。交付が受けられるかの確認もできますのでご相談ください。
社会保険等に加入している人はご自身の加入する保険者へお問い合わせください。
| 区分 | 標準負担額減額認定証の提示 | 入院時食事療養標準負担額 | |
|---|---|---|---|
| 子ども又はひとり親家庭等 | 不要(補足)1 | 無料 | |
| 重度心身障害者
又は 高齢重度障害者 |
住民税課税世帯 | 交付対象外 | 自己負担(510円) |
| 住民税非課税世帯等 | 提示(補足)2 | 無料 | |
| 未提示 | 自己負担(510円) | ||
(補足)1子ども又はひとり親家庭等は、標準負担額認定証がなくても食費は無料になりますが、提示をしていただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。この制度を将来にわたり安定して運営していくために、交付が受けられる人は標準負担額認定証の提示のご協力をお願いします。
(補足)2重度心身障害者又は高齢重度障害者で住民税非課税世帯等の人は標準負担額減額認定証を入院の際に医療機関に提示又は電子的確認をした場合のみ無料となります。標準負担額減額認定証を退院後に提示又は電子的確認をしても還付等は受けられないので、ご注意ください。
お願い
学校などでケガをした場合は
子どもが保育所や幼稚園、小・中・高等学校(登下校中を含む)でケガをして医療機関・接骨院等を受診した場合、所定の手続きをすると、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」から見舞金や医療費が支給されることがあります。医療費は福祉医療制度で一時的に立て替えていますので、学校などでケガをして医療機関・接骨院等を受診する(した)場合は、必ず学校などに連絡してください。(災害共済給付の申請方法については学校等にお問い合わせください)。