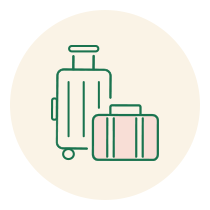介護保険サービス
介護保険制度
介護保険制度は、だれもが安心して老後の生活を送ることができるよう、老後の不安要因である「介護」を社会全体で支え合う制度です。住み慣れた地域で必要な介護サービスを総合的に利用できる仕組みになっています。
保険者(運営主体)
市町村(渋川市)が保険者として、介護保険事業を運営しています。
被保険者 (加入者)
市内に住所がある人で40歳以上の人が自動的に加入者(被保険者)になります(市外の特別養護老人ホームや養護老人ホーム等に入所し、住所変更した人も含みます)。
|
項目 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
|---|---|---|
|
加入者 |
65歳以上の人 |
40歳から64歳までの医療保険 (国民健康保険、健康保険など) に加入している人 |
|
保険料 |
市民税の課税状況や所得に応じて決定 |
加入している医療保険の 算定方法に基づき決定 |
|
保険料の 納め方 |
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金の 受給額が年額18万円以上の人は、 年金からの天引き(特別徴収)(注意1) それ以外の人は、個別に納付書で納付(普通徴収) |
医療保険料と合わせて納付 |
|
サービスを 利用できる人 |
介護(支援)が必要と認定された人 |
特定疾病(注意2)により介護(支援) が必要と認定された人 |
(注意1)こんなときは納付書払い(普通徴収)になります。
- 年度の途中で65歳になった人
- 年度の途中で他市町村から転入してきた人
- 年度の途中で年金からの天引き(特別徴収)ができなくなった人など
(補足)納付書払いの人は口座振替ができます。詳細はリンクをご確認ください。
(注意2)特定疾病(以下の16疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料(65歳以上の人)
|
所得段階 |
対象となる人 |
負担割合 |
保険料 (年額) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 |
80 万円9千円以下で、同じ世帯に市民税課税者がいない人 |
基準額 ×0.285 |
20,200円 |
|||
| 第2段階 |
本人及び世帯が住民税非課税者で 右のいずれかの方 |
80万9千円超 120万円以下 |
基準額 ×0.485 |
34,500円 | ||
| 第3段階 | 120万円超 |
基準額 ×0.685 |
48,700円 | |||
| 第4段階 |
本人が住民税非課税者で 世帯内に住民税課税者がいる場合で 右のいずれかの方 |
80万 9千円以下 |
基準額 ×0.90 |
64,000円 | ||
| 第5段階 |
80万 9千円超 |
基準額 ×1.0 |
71,200円 | |||
| 第6段階 |
本人が住民税課税者で 前年の合計所得金額が右のいずれかの方 |
120万円未満 |
基準額 ×1.2 |
85,400円 | ||
| 第7段階 |
120万円以上 210万円未満 |
基準額 ×1.3 |
92,500円 | |||
| 第8段階 |
210万円以上 320万円未満 |
基準額 ×1.5 |
106,800円 | |||
| 第9段階 |
320万円以上 420万円未満 |
基準額 ×1.7 |
121,000円 | |||
| 第10段階 |
420万円以上 520万円未満 |
基準額 ×1.9 |
135,200円 | |||
| 第11段階 |
520万円以上 620万円未満 |
基準額 ×2.1 |
149,500円 | |||
| 第12段階 |
620万円以上 720万円未満 |
基準額 ×2.3 |
163,700円 | |||
| 第13段階 | 720万円以上 |
基準額 ×2.4 |
170,800円 | |||
(補足)合計所得金額から、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額で所得段階判定を行います。
(補足)本人及び世帯が住民税非課税者の場合には、合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額で所得段階判定を行います。
(補足)第1段階から第3段階の保険料は、負担軽減措置により国・県・市の公費を充てることにより軽減されています。
被保険者証
65歳になる月の初旬に、住民票のある住所に被保険者証を郵送します。40歳から64歳までの人は、要支援・要介護と認定された人に交付されます。
他市町村から転入してきたとき
- 転入手続きのときに、本人確認が取れた人について被保険者証をお渡しします。それ以外の人は後日郵送します。
- 転入前の市町村で要支援・要介護認定を受けている人は、渋川市でその要介護度を引き継ぐことができます。転入手続きのときに、転入前の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて申請してください。
サービス利用の手順
要介護認定の申請
市役所本庁舎介護保険課、各行政センターの窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
申請に必要なもの
訪問調査
認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。また、市から主治医に対し、心身の状況についての意見書作成を依頼します。
審査・判定
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度(要介護度)を審査・判定します。判定は「非該当」、「要支援1から2」、「要介護1から5」に区分されます。
認定結果の通知
審査会の結果に基づき、要介護度が認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証をお送りします。
ケアプラン・介護予防ケアプランの作成
要支援1から2と認定された人
心身の状態の維持・改善を目指し、介護予防サービスが利用できます。なお、介護予防サービスを利用するには、介護予防ケアプランの作成が必要です。渋川市地域包括支援センターもしくは同センターから委託された居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所が支援します。
要介護1から5と認定された人
自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。なお、在宅サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。居宅介護支援事業所が支援します。
施設に入所する場合は、直接施設へお申し込みください。
利用できるサービス
在宅サービス
通所型
通所介護(デイサービス)、通所型サービス
通所介護施設で、食事、入浴などの支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション
医療施設などで、食事、入浴、機能訓練などのリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問型
訪問介護(ホームヘルプ)、訪問型サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事など身の回りの援助を行います。
訪問入浴介護、予防訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士などが家庭を訪問し、機能訓練を行います。
訪問看護、介護予防訪問看護
看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に基づき看護を行います。
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
福祉用具・住宅改修
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
品目
車いす(付属品含む)、特殊寝台(同)、床ずれ防止用具、体位変換器(起き上がり補助装置を含む)、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(同)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器(離床センサーを含む)、移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
要支援1から2および要介護1の人は原則、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえのみ対象
(補足)スロープ・歩行器・歩行補助つえは購入と選択出来ます。
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
指定を受けた販売店で購入した福祉用具の費用について、年間10万円を上限に利用者負担の割合分(1割~3割)を除いた金額を支給します。
品目
腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
(補足)スロープ・歩行器・歩行補助つえは貸与と選択出来ます。
住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消など行った際、20万円を上限に利用者負担の割合分(1割~3割)を除いた金額を支給します。
(補足)事前申請が必要です。
短期入所(ショートステイ)
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護を行います。
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所し、介護を行います。
特定施設生活介護
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
施設サービス(要支援1から2の人は利用できません)
施設入所
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅で生活することが困難な人に介護を行う施設です。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心に介護を行う施設です。
介護医療院
長期の療養が必要な人の医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。
地域密着型サービス
地域密着型サービス事業所について
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に利用者の選択に応じて、訪問型のサービスや泊りのサービスを組み合わせて提供する小規模な拠点です。
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の人は利用できません)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要支援の人は利用できません)
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。
地域密着型通所介護(要支援の人は通所型サービスでの利用となります)
定員数が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの支援を日帰りで行います。
利用の費用
利用者負担は、介護保険サービスにおいてかかった費用の1割から3割です。利用者負担の割合については、要介護(要支援)認定者に介護保険負担割合証が毎年交付されます。なお、要介護度別に利用できる上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額を超えて利用することもできますが、超えた部分の費用は全額自己負担となります。(補足)第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、原則1割負担です。
2割負担となる人は、次の要件の両方に当てはまる人のことです。
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が、単身で280万円以上、2人以上で346万円以上
3割負担となる人は、次の要件の両方に当てはまる人のことです。
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が、単身で340万円以上、2人以上で463万円以上
在宅サービスの費用
在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて支給限度額が決められています。支給限度の範囲内でサービスを利用する場合、利用者負担は1割~3割(過去に保険料を2年以上滞納したことで給付制限を受けている場合は3割~4割)ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
|
要介護度 |
支給限度単位 |
|---|---|
|
要支援1 |
5,032単位 |
|
要支援2 |
10,531単位 |
|
要介護1 |
16,765単位 |
|
要介護2 |
19,705単位 |
|
要介護3 |
27,048単位 |
|
要介護4 |
30,938単位 |
|
要介護5 |
36,217単位 |
実際の費用は「単位数×渋川市の地域単価(サービスの種類に応じ10円から10.21円)」によって算定されます。
また、特定福祉用具販売、住宅改修費支給、居宅療養管理指導は上記の支給限度単位とは別枠のサービスです。
|
単価 |
サービス種類 |
|---|---|
|
10.21円 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 居宅介護支援、介護予防支援 |
| 10.17円 |
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 |
| 10.14円 |
通所介護、短期入所療養介護、特定入所者生活介護、地域密着型通所介護、 認知証対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 10円 | 居宅療養管理指導、福祉用具貸与 |
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合、(1)サービス費用の1割~3割+(2)食費+(3)居住費+(4)日常生活費が利用者負担となります。
所得状況により、下表のとおり食費と居住費の自己負担額が減額になります。なお、減額を受けるためには申請が必要です。
|
負担 段階 |
条件 |
居住費 (滞在費) |
食費
(施設入所者) |
食費 (短期入所者) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第 1 段 階 |
・本人及び世帯全員が 住民税非課税であって、 老齢福祉年金の受給者 ・生活保護を受給している方 |
多床室 |
0円 |
300円 | 300円 | |
|
従来型 個室 |
特養 | 380円 | ||||
|
老健・ 医療院等 |
550円 | |||||
|
ユニット型 個室的多床室 |
550円 | |||||
| ユニット型個室 | 880円 | |||||
|
第 2 段 階 |
本人及び世帯全員が 住民税非課税であって、 合計所得金額+年金収入額と 非課税年金収入額の合計が 年額80万9千円以下の方 |
多床室 |
430円 |
390円 | 600円 | |
|
従来型 個室 |
特養 |
480円 |
||||
|
老健・ 医療院等 |
550円 | |||||
|
ユニット型 個室的多床室 |
550円 | |||||
| ユニット型個室 | 880円 | |||||
|
第 3 段 階 1 |
本人及び世帯全員が 住民税非課税であって、 合計所得金額+年金収入額と 非課税年金収入額の合計が 年額80万9千円超 120万円以下の方 |
多床室 |
430円 |
650円 | 1,000円 | |
|
従来型 個室 |
特養 | 880円 | ||||
|
老健・ 医療院等 |
1,370円 | |||||
|
ユニット型 個室的多床室 |
1,370円 | |||||
| ユニット型個室 | 1,370円 | |||||
|
第 3 段 階 2 |
本人及び世帯全員が 住民税非課税であって、 合計所得金額+年金収入額と 非課税年金収入額の合計が 年額120万円超の方 |
多床室 |
430円 |
1,360円 | 1,300円 | |
|
従来型 個室 |
特養 | 880円 | ||||
|
老健・ 医療院等 |
1,370円 | |||||
|
ユニット型 個室的多床室 |
1,370円 | |||||
| ユニット型個室 | 1,370円 | |||||
|
対 象 外
|
上記に該当しない方、また上記に該当する場合でも下記に該当する方は対象外になります。 | |||||
|
1.配偶者が住民税課税の方 |
||||||
|
2.預貯金額が一定額を超える方 |
||||||
|
・第1段階の方 |
単身1,000万円、夫婦2,000万円 | |||||
| ・第2段階の方 | 単身650万円、夫婦1,650万円 | |||||
| ・第3段階1の方 | 単身550万円、夫婦1,550万円 | |||||
| ・第3段階2の方 | 単身500万円、夫婦1,500万円 | |||||
|
(補足) 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、各負担段階にかかわらず 単身1,000万円、夫婦2,000万円 |
||||||
(補足)短期入所者:ショートステイ((介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護)利用者
(補足)特養:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(補足)老健・医療院等:介護老人保健施設・介護医療院
また、対象とならない場合でも特例で対象となること(特例減額措置)があります。詳しくはお問い合わせください。
高額介護サービス費
同じ月内に利用したサービスの利用者負担の合計額が上限額を超えた場合、超えた部分が高額介護サービス費として支給されます。
|
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 (月額) |
|---|---|
|
生活保護の受給者 |
15,000円(世帯) |
|
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超える人 |
24,600円(世帯) |
|
住民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 |
44,400円(世帯) |
|
住民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)以上 690万円(年収約1,160万円)未満の人 |
93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯の方で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 140,100円(世帯) |
支給対象になるときは、市役所から案内通知をお送りします。
(補足)令和7年7月利用分までは「課税年金収入額が80万9千円」と文言は「課税年金収入額が80万円」と読み替えとなります。
社会福祉法人が運営するサービスを利用した場合の軽減措置
低所得で生活困難な方((補足)一定の要件があります。)が、県へ軽減実施の申し出を行った社会福祉法人の介護保険サービスを利用した場合に、利用者負担額の一部軽減が受けられる制度があります。市の窓口に申請し、利用者負担軽減確認証の交付を受けることが必要です。
減免措置
災害その他特別の事情がある場合に第1号被保険者保険料等の減免を受けられる制度があります。市の窓口に申請が必要です。